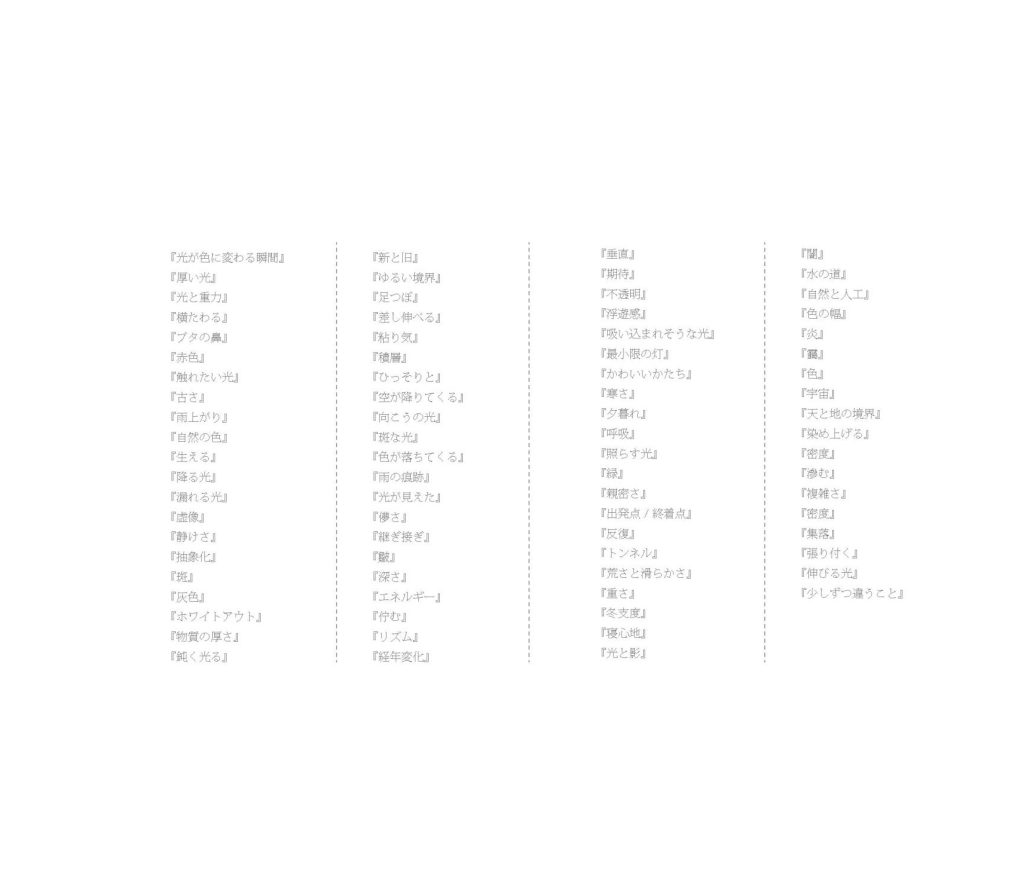text

0章 雰囲気との出会い
オーストリア最西端の都市フェルトキルヒにある設計事務所に勤務した半年の間、列車に乗りたくさんの風景や建築を訪ねた。そこで出会った風景や建築の多くは言葉を失うほど美しく全身を貫くものばかりだった。レマン湖沿いを走る列車の車窓からみた風景は、建築、自然、生活、現象が不可分に存在し、その総体として私の目の前に唯一無二の在り方として現れていた。
1章 研究背景/ 目的
雰囲気を建築やその空間の重要な要素と位置づけ、その在り方が絶え間なく動き続ける準物体的建築の設計を目的とする。
そこで哲学者ヘルマン・シュミッツ(HermannSchmitz, 1928-)が提唱した準物体(quasi-object)、及びゲルノート・ベーメ(Gernot Böhme, 1937-)が提唱する雰囲気(atmosphere)というふたつの概念に着目し、建築やそれを取り巻く自然や風景がつくりだす雰囲気の記録を建築設計における重要な要素とし、物や人間、建築や自然などが相互に関連し合い、呼応して生まれる準物体的建築の設計を試みる。
2章 準物体とは
シュミッツによれば、準物体とは「その性格が不安定で知覚経験に現れる限りでのみ存在するものである」という。また、ベーメは「準物体は、現在性という存在方法においてのみ存在しうる」ものとして私たちの生活の中に存在するという。彼らは、そのような準物体の例として、風、眼差し、声、匂い、色、音、雨音など、特徴的な物、繰り返し現れる痛み、寒さ、暑さ、静寂、暗闇、時間などをあげる。
つまり準物体とは、コップやりんごのように物体として不変的な形態は持たないが私たちの知覚経験の中には確かに存在し、その在り方が極めて動的であり、実際にその状態を経験した者にしか感じることができない質をそなえたものだといえる。
3章 雰囲気とは
私たちは、視覚、聴覚、臭覚などの感官を個別的に用いることで対象を認識すると一般的に理解されている。それは知覚する主体(人間)とその対象である客体(もの)が分離した状態である。しかし、ベーメは上記の知覚以前に雰囲気の知覚というものがあるという。それは知覚における第一次的な対象であり、視覚、味覚、臭覚、聴覚などの特定の感官でのみで捉えられるものではなく、複数の感官によって共有される共感覚に根ざすものであると定義する。
つまり、雰囲気とは建築や人間、ものや自然がある時間の中に同時に存在し、その在り方が溶け合うことによって生まれる要素であり、認識する主体(人間)とその対象である客体(もの)という主客二元論を超えた、建築、人間、自然、物が呼応して存在するための非常に重要な建築の要素であるとえる。
4章 準物体的建築とは
建築は物質として現れるとそれが物理的な外力を受けない限り実体として変化することはない。従って建築がシュミッツのいう準物体それ自体になりうることはできない。しかし、その経験者の知覚経験においてでしか現れない唯一無二の建築の在り方は作り出すことができると考える。
つまり準物体的建築とは、実体としては不変のものとして強く存在するが、人間の知覚に現れるその建築の在り方が極めて動的な建築のことである。
5 章 準物体的建築と雰囲気
私たちが建築を設計する際に操作するさまざまなパラメーターは、大学教育においてその基礎知識をを学ぶことができる。例えば建築計画、環境設備、構造力学などがそれであり、身につけた知識と現場での経験の積み重ねによって多くの建築をうみだすことができる。では、準物体的建築の設計においてその構成要素として雰囲気を導入するにあたり、私たちは何からその雰囲気地というを身につけることができるのだろうか。
準物体的建築の構成要素としての雰囲気は、ある時間の幅の中に複数のものが存在することによって生まれる非常に現実性の高いものであり、身体を持ってそこに在ることが重要である。したがって、雰囲気とは机上では学ぶことができない、自らが身体をもってその建築や空間を経験することが必要条件となる。
6章 雰囲気を記録すること
準物体的建築を設計する際の重要な要素として雰囲気を導入する。雰囲気とは極めて現実性の高いものであり、自らの雰囲気の経験の蓄積が非常に重要である。本研究では建築やそれを取り巻く自然や風景の空間経験を写真と言語という二つの媒体によって記録した。
6章の1 写真
写真という媒体を選択した理由として、ロラン・バルト(Roland Barthes, 1915-1980)の写真論を参照する。バルトは、写真には2つの要素があるとしそれらをストゥディウム(studium)とプンクトゥム(Punctum)と名付けた。前者は写真の中から得られる私たちの知識や教養などの一般的関心にかかわる情報といった要素であり、後者はそうした一般的な関心を破壊するものであり、写真の場面から発し、見る人を突き刺しにやって来るものだという。そして、写真において重要なことはこの二つが共存していることだという。
ストゥディウムは写真の中に私たちが写真家の意図に共感し、理解し、学習する可能性を与える。また、プンクトゥムは写真にそれをみる人の数だけの在り方を与えると言える。
建築にもこのストゥディウムとプンクトゥムがあり、雰囲気とは実際にその建築を経験した人間に襲いかかってくるプンクトゥムのようなものだと考えることができないだろうか。雰囲気を記録するにあたり、両者の要素を持ち合わせることができる写真という記録媒体を用いることは適していると考える。
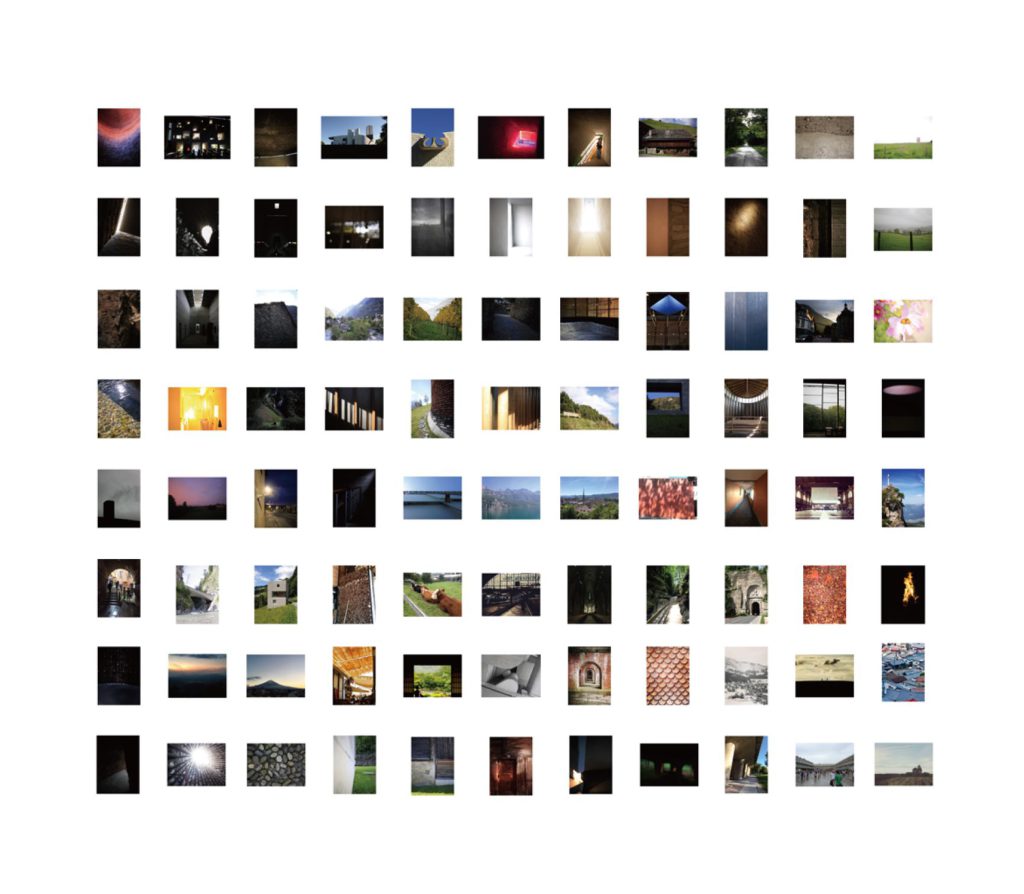
6章の2 言語
プンクトゥムによって、見た人の数だけその在り方が存在する写真という媒体は、自己の経験を記録するには必要条件ではあるが十分条件ではない。そこでもうひとつの記録媒体として言語を導入することでその不足を補うこととする。
経験を言語化する行為は非常に主観的な側面をもつ一方で、言語自体は抽象性を持った客観的な媒体であり、経験と制作行為を繋ぐ重要な役割を果たすと考える。また、建築を設計する側と依頼する側というふたつの立場をつなぐ道具として、図面、模型、CG イメージなどと同様に、言語もまた他者と思考を共有する重要なツールであることは間違いない。従って、雰囲気を言語化することは非常に重要な行為であると考える。